やむを得ない事情で、大切な方の訃報に接しながらも葬儀に参列できない状況は、誰にとっても心苦しいものです。特に、長年親交のあった親族や、苦楽を共にした親しい友達の葬儀であれば、その想いは一層強くなることでしょう。すぐにでも駆けつけたい気持ちとは裏腹に、遠方に住んでいたり、病気療養中であったり、どうしても外せない仕事があったりと、様々な理由で参列が叶わないことは少なくありません。
そのような時、多くの方が頭を悩ませるのが、ご遺族への連絡方法です。お通夜に行けない旨をメールで親戚や友達にどう伝えるべきか、失礼のない適切な葬儀欠席のお詫びの文例を探している方も多いのではないでしょうか。
また、葬儀に参列できない代わりに、せめてもの弔意を形にして伝えたいと考えたとき、多くの方が供花を検討されます。しかし、葬儀に参列できない場合の挨拶として供花を贈る際にも、守るべきマナーや手順があります。良かれと思ってしたことが、かえってご遺族の負担になってしまっては元も子もありません。葬儀欠席のお詫びをメールで伝えることと併せて、後日のトラブルを避けるためにも、正しい知識を身につけておくことが大切です。
この記事では、そうした状況で役立つ、葬儀に参列できない場合のメール例文を、親戚向けや友達向けといった関係性ごとに解説するとともに、弔意を示すための供花に関するあらゆる疑問にお答えします。葬儀に参列できない際の文例から、宗教・宗派ごとの違い、供花の手配方法、費用相場まで、失敗や後悔のないお見送りができるよう、具体的かつ分かりやすくまとめています。
この記事を読むことで、以下の点について理解を深めることができます
- 葬儀に参列できない場合に送るメールの基本的な書き方と文例
- 弔意を示すための供花を贈る際に押さえるべき基本的なマナー
- 故人との関係性や状況に応じた供花の費用相場と単位
- 失敗しないための供花の手配方法と注文時の具体的な注意点
葬儀に参列できない時のメール例文と弔意の示し方
- 押さえておきたいお通夜の供花マナー
- 葬儀の花はどこに頼むのが最適か
- 失敗しない葬儀の生花の注文の仕方
- 葬式の花でダメと言われる理由
- 家族葬の供花は親族どこまでが適切か
押さえておきたいお通夜の供花マナー
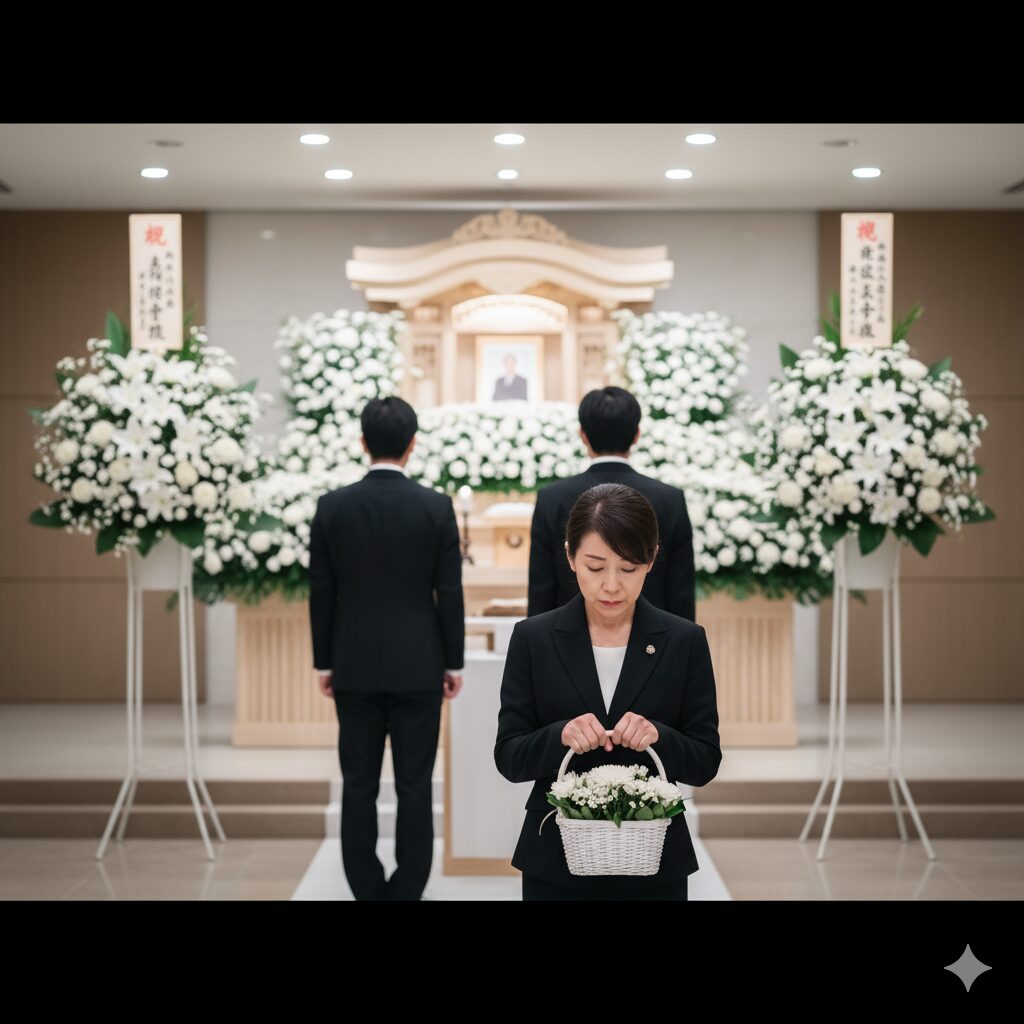
お通夜や葬儀に参列できない代わりに供花で弔意を示す場合、故人とご遺族への配慮を第一に考え、マナーを守ることが何よりも大切です。マナー違反は、かえってご遺族に負担をかけたり、不快な思いをさせてしまったりする可能性があるため、手配の前に必ず確認すべきポイントがいくつかあります。
最優先事項:供花辞退の意向がないか確認する
まず最初に、そして最も重要視すべきは、ご遺族が供花を辞退していないかという点です。近年増えている家族葬や、故人の遺志により、香典や供花を一切辞退されるケースが少なくありません。
訃報の案内に「誠に勝手ながら、御香典、御供花、御供物の儀は固くご辞退申し上げます」といった一文が記載されている場合は、その意向を尊重し、供花を贈るのは控えましょう。この場合、無理に贈ってしまうと、ご遺族は返礼の準備などでかえって負担を感じてしまいます。弔意を示したい気持ちは分かりますが、何もしないことが最善の配慮となることを理解しましょう。
ポイント:ご遺族の意向が最優先
訃報の案内に「供花辞退」の旨が記載されていたら、弔意を示したい気持ちがあっても、贈らないのがマナーです。ご遺族の気持ちを尊重しましょう。
宗教・宗派による違いを理解する
次に、宗教・宗派の確認も欠かせません。葬儀の形式によって、ふさわしいお花の種類や形式が大きく異なるためです。
- 仏式:一般的にイメージされる、菊や百合、蘭などを用いたスタンド花やアレンジメントフラワーが主流です。白を基調としますが、淡い色合いの花が加えられることもあります。
- 神式:榊(さかき)を用いたり、仏式と同様に白い花を基調とした生花が用いられたりします。ただし、神式では「御玉串料」として金品を贈ることが多く、供花は近親者のみに限定される場合もあります。
- キリスト教式:日本の仏式のような名札を立てた「供花」は飾りません。代わりに、名札を付けずにバスケットなどに生花をアレンジした「フラワーアレンジメント」や、献花用の花を自宅に贈るのが一般的です。花の種類は、白いカーネーションや百合、蘭などがよく用いられます。カトリックかプロテスタントかによっても慣習が異なる場合があるため、不明な場合は葬儀社に確認するのが確実です。
宗派が不明な場合は、どのような宗教にも対応しやすい、白を基調とした洋花のアレンジメントを選ぶのが無難と考えられます。
供花を手配するタイミング
供花を手配するタイミングも重要です。早すぎても斎場の準備が整っておらず、遅すぎても葬儀に間に合いません。
- 最適なタイミング:お通夜の開始時刻の2~3時間前までには届くように手配するのが望ましいです。これにより、斎場のスタッフが祭壇の準備と共に、供花を適切な場所に配置する時間を確保できます。
- 遅くとも:お通夜に間に合わない場合でも、告別式が始まる前までには必ず届くようにしましょう。
斎場によっては外部からの花の持ち込みに関するルール(時間指定や業者の指定など)が定められている場合もあるため、事前に葬儀社へ確認しておくと、よりスムーズで確実です。
葬儀の花はどこに頼むのが最適か

葬儀で贈る供花の手配先はいくつか選択肢があり、それぞれにメリットと注意点が存在します。どこに依頼するのが最適かは、ご自身の状況や希望によって異なりますが、それぞれの特徴を理解して選ぶことが大切です。
① 葬儀を担当している葬儀社
最も一般的で確実な方法は、その葬儀を担当している葬儀社へ直接依頼することです。
葬儀社に依頼する最大のメリットは、斎場のルールや祭壇の規模、全体のデザインや色合いの統一感をすべて把握している点にあります。祭壇のデザインに合わせた花の種類やサイズを選んでくれるため、他の供花とのバランスが崩れる心配がありません。また、名札の表記(会社名や肩書など)や設置場所の序列についても間違いなく手配してくれるため、安心して任せられます。
依頼する際は、訃報の連絡を受けた際に担当の葬儀社名と連絡先を確認し、「〇〇家様のご葬儀に供花をお贈りしたいのですが」と伝えれば、スムーズに対応してもらえます。
② 生花店(フラワーショップ)
日頃から付き合いのある生花店や、故人のイメージに合わせた独自のデザイン性の高いアレンジメントを希望する場合などは、直接生花店に依頼する方法もあります。
この方法のメリットは、花材やデザインの自由度が高い点です。故人が好きだった花を入れたい、特定の色合いでまとめてほしい、といった細かな要望に応えてもらいやすいでしょう。
ただし、この場合は自分で斎場の住所、日時、喪主名、故人名などを正確に伝えなければなりません。加えて、斎場によっては外部の生花店からの持ち込みが禁止されていたり、持ち込み料が発生したりするケースもあるため、必ず注文前に葬儀社へ確認が必要です。確認を怠ると、せっかく手配した花が飾れないという事態にもなりかねません。
③ インターネット通販サイト
最近では、供花を専門に扱うインターネット通販サイトも増えています。24時間いつでも注文できる手軽さが魅力です。
価格帯が広く、比較検討しやすいのがメリットですが、注意点もあります。サイトによっては、提携している地域の生花店から配送されるため、品質やデザインがウェブサイトの写真と若干異なる可能性があります。また、名札の細かい指定(旧字体の漢字など)に対応できない場合や、配送時間の厳密な指定が難しいこともあるため、急ぎの場合や特別な要望がある場合は特に慎重に選ぶ必要があります。信頼できるサイトかどうか、運営会社の情報や口コミなどを確認してから注文すると良いでしょう。
| 手配先 | メリット | デメリット・注意点 |
|---|---|---|
| 葬儀社 | ・斎場のルールや統一感を把握しており確実 ・名札や設置場所も序列通りで間違いがない ・手続きが最もスムーズで安心感が大きい |
・提携している生花店の花になるため、デザインの自由度は低い場合がある ・価格帯の選択肢が限られることがある |
| 生花店 | ・独自のデザインや希望の花材を選びやすい ・故人のイメージに合わせたアレンジが可能 ・直接相談しながら決められる |
・斎場への持ち込み可否を自分で確認する必要がある ・喪主名や日時、斎場のルールなどを正確に伝える手間がかかる ・持ち込み料が発生する場合がある |
| ネット通販 | ・24時間いつでもパソコンやスマホから注文できる ・価格帯が広く、比較検討しやすい ・遠方からでも手軽に手配できる |
・品質やデザインが見本と異なる可能性がある ・細かい時間指定や名札の特殊な指定が難しい場合がある ・トラブル時の対応に時間がかかることがある |
失敗しない葬儀の生花の注文の仕方

葬儀の生花、すなわち供花を注文する際には、いくつかの情報を事前に整理しておくことで、手配が円滑に進み、間違いを防ぐことができます。特に葬儀社以外に依頼する場合は、情報が不正確だと大きな迷惑をかけてしまうことになります。慌てて注文して名札の名前を間違えたり、届ける場所を誤ったりすると、大変失礼にあたります。
供花注文前のチェックリスト
以下の情報をメモなどにまとめてから連絡することで、注文がスムーズになるだけでなく、手配ミスという最も避けたい事態を防ぐことにつながります。
- お通夜・告別式の日時と場所:斎場の正式名称、住所、電話番号、ホール名まで正確に。
- 故人様と喪主様のお名前:漢字を間違えないよう、フルネームで確認。
- 名札に記載する芳名(ふだめい):個人名か連名か、会社名・役職などを明確に。
- 宗教・宗派:分かれば伝える。不明な場合は「宗派不明」と正直に伝える。
- 予算と花の形式(基数):「一基(いっき)」か「一対(いっつい)」かを明確に。
- 自身の連絡先:注文者の名前と、日中連絡が取れる電話番号。
名札に記載する芳名の具体例
名札は誰から贈られた花なのかを示す重要なものです。書き方にはいくつかのパターンがあります。
| 贈り主のパターン | 名札の表記例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 個人 | 田中 太郎 | フルネームで記載するのが基本です。 |
| 夫婦連名 | 田中 太郎 花子 |
夫の名前をフルネームで書き、その左に妻の名前のみを記載します。 |
| 会社(法人) | 株式会社〇〇 代表取締役社長 田中 太郎 |
会社名と役職、氏名を記載します。会社名のみの場合もあります。 |
| 友人・孫など複数名 | 友人一同 | 人数が多い場合は「〇〇一同」とまとめるのが一般的です。3名程度までなら個人名を列記することもあります。 |
| 連名(序列あり) | 田中 太郎 鈴木 次郎 佐藤 三郎 |
役職や年齢順に右から左へ記載するのがマナーです。 |
これらの情報を正確に伝えることで、贈り主の弔意が正しくご遺族に伝わります。特に連名の場合は、名前の順番を間違えると失礼にあたるため、事前にしっかりと確認しましょう。
葬式の花でダメと言われる理由

葬式の場に供える花、すなわち供花には、一般的に避けるべきとされる種類があります。これらは古くからの慣習や宗教的な理由、あるいはご遺族や他の参列者への配慮に基づいています。これらを知らずに贈ってしまうと、意図せずともご遺族に不快な思いをさせてしまう可能性があるため、その理由と共に理解しておくことが大切です。
一般的に避けられる花とその理由
- トゲのある花(バラ、アザミなど):トゲが「殺生」や「傷」を連想させるため、仏教の教えに反すると考えられています。
- 香りの強い花(一部のユリ、クチナシなど):お焼香の香りを妨げたり、狭い屋内で気分が悪くなる方がいたりすることへの配慮から避けられます。
- 派手な色の花(真っ赤、ショッキングピンクなど):「お祝い」のイメージが強く、故人を偲ぶ厳粛な場にはふさわしくないとされています。
- 花粉が多い花:祭壇や参列者の衣服を汚してしまう可能性があるため、特にユリなどは花粉を取り除いてから使用されるのが一般的です。
- 毒性のある花(彼岸花、すずらんなど):縁起が悪いとされるほか、小さなお子様などが誤って触れる危険性を避けるためです。
- 鉢植えの花:根付くことが「寝付く(病気が長引く)」を連想させ、縁起が悪いとされるため、お悔やみの場全般でタブーとされています。
ただし、これらの慣習は絶対的なものではなく、近年では少しずつ変化も見られます。例えば、故人が生前バラの花をこよなく愛していた場合など、ご遺族の希望があれば、あえてその花を飾る「花祭壇」なども増えています。
もし故人が好きだった花が一般的にタブーとされる種類だった場合、贈りたい気持ちがあれば、まずはご遺族か葬儀社に「故人様が生前お好きだった〇〇のお花をお贈りしたいのですが、ご迷惑ではないでしょうか」と、控えめに相談してみるのが良いでしょう。最終的には、ご遺族の気持ちを尊重することが最も重要です。
迷った場合は、白を基調とし、淡い紫や青、グリーンなどを加えた落ち着いた色合いの、香りが控えめな花(菊、カーネーション、胡蝶蘭、トルコギキョウなど)を選ぶのが、最も間違いのない選択と言えます。
家族葬の供花は親族どこまでが適切か

近年主流となっている家族葬において、供花を贈るかどうか、また親族であればどこまでの範囲が贈るべきかという点は、多くの方が悩む問題です。一般葬とは異なる家族葬ならではの配慮が求められます。
この問題に対する最も重要な答えは、前述の通り「ご遺族の意向を最優先する」ということです。
家族葬は、その名の通り家族やごく親しい近親者のみで、外部からの弔問などを気にすることなく、静かに故人を見送ることを目的としています。そのため、参列者の範囲を限定するのと同様に、香典や供花、弔問などを一律で辞退されるケースが非常に多く見られます。
訃報の連絡に「供花・供物は固くご辞退申し上げます」といった一文が添えられている場合は、たとえご自身の親や兄弟といった極めて近しい親族であってもその意向に従い、供花を贈るのは控えるのがマナーです。
供花辞退の記載がない場合の対応
もし訃報に供花辞退の明確な記載がない場合でも、「記載がないから贈っても良いだろう」と自己判断するのは早計です。念のためご遺族に直接確認するのが最も確実な方法です。
ただし、葬儀前の多忙なご遺族に電話で長々と問い合わせるのは負担をかけてしまいます。可能であれば、喪主以外の連絡が取りやすい親族に尋ねるか、以下のような簡潔なメッセージで相手の都合を気遣いながら確認するのが良いでしょう。
「この度はご愁傷様です。心ばかりのお花をお贈りしたいと考えているのですが、ご迷惑ではないでしょうか。ご不要でしたら、どうぞご遠慮なくお申し付けください。」
このように、相手が断りやすいような聞き方をすることが、思いやりのある対応と言えます。
親族の範囲について
「どこまでの親族が贈るべきか」という点について、法的な定義や明確な決まりはありません。判断基準となるのは、故人との生前の関係性の深さです。
もしご遺族が供花を受け付けている場合、一般的には故人の子供や兄弟姉妹、孫といった関係であれば、弔意を示すために贈ることが多いと考えられます。故人のおいやめい、いとこなど、少し遠い親戚の場合は、他の親族と連名で一つの供花を贈るという選択肢もあります。
いずれにしても、家族葬の場合は「親族だから贈るのが当たり前」という考えは一度脇に置き、まずはご遺族の気持ちと状況を確認するという姿勢が何よりも大切になります。供花の代わりに、後日改めてご自宅へ弔問に伺ったり、お悔やみの手紙を送ったりすることも、弔意を伝える立派な方法です。
葬儀に参列できない場合の供花手配とメール例文
- 個人の供花の相場はいくら?
- 供花一基あたりの値段の目安
- 友人一同で出す供花の相場
- 葬式の花を孫一同で贈る値段
- 葬儀の供花代は誰が払うもの?
個人の供花の相場はいくら?

個人として供花を贈る際の費用相場は、一般的に15,000円から30,000円程度が目安とされています。この金額は、故人との関係性の深さはもちろんのこと、ご自身の年齢や社会的立場、そしてお住まいの地域の慣習によっても変動します。
例えば、会社の同僚や一般的な友人・知人といった関係であれば、15,000円から20,000円程度の供花を選ぶことが多いようです。これは、相手に過度な気を遣わせることなく、かつ弔意をきちんと示すことができるバランスの取れた価格帯と考えられています。
一方で、学生時代からの特に親しかった友人や、大変お世話になった会社の直属の上司、あるいは親族といった深い関係性の場合は、20,000円から30,000円程度の、より見栄えのする供花を選ぶ傾向にあります。これは、感謝と悲しみの気持ちをより強く表現したいという想いの表れと言えるでしょう。
供花の価格は、主に使われる花の種類(胡蝶蘭や百合など高価な花)、花の量、そしてスタンド全体の大きさによって決まります。価格が高いものほど、大きく立派になり、祭壇での見栄えも良くなります。ただし、あまりに高額すぎる供花(例えば50,000円以上)を個人で贈ることは、かえってご遺族に「これほど高価なものをいただいてしまって…」と恐縮させてしまう可能性もあるため、注意が必要です。
重要なのは金額そのものよりも、故人を悼む気持ちです。相場はあくまで一つの目安として捉え、ご自身の経済状況と故人への想いを考慮して、無理のない範囲で心を込めて選ぶことが最も大切と言えます。
| 故人との関係性 | 費用相場の目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 友人・知人 | 15,000円 ~ 20,000円 | 一般的なお付き合いの場合の標準的な価格帯です。 |
| 会社の同僚・上司・部下 | 15,000円 ~ 25,000円 | 特にお世話になった方には、少し高めの予算で考えることもあります。 |
| 取引先関係者 | 20,000円 ~ 30,000円 | 会社として贈る場合は、慶弔規定などを確認しましょう。 |
| 特に親しい友人 | 20,000円 ~ 30,000円 | 深い弔意を示すため、相場より少し高めの価格帯が選ばれる傾向にあります。 |
| 親族(叔父・叔母・いとこ等) | 20,000円 ~ 30,000円 | 親族間で相談し、金額を合わせる場合もあります。 |
供花一基あたりの値段の目安

供花を注文する際、必ず知っておきたいのが「基(き)」と「対(つい)」という独特の単位です。この違いを理解していないと、予算が倍になってしまう可能性もあるため、しっかりと押さえておきましょう。
- 一基(いっき):供花スタンド1つのことを指します。
- 一対(いっつい):同じ供花スタンド2つ(一組)のことを指します。
前述した個人の供花の相場(15,000円~30,000円)は、基本的に「一基」あたりの値段を指しています。したがって、もし一対で供花を贈りたい場合は、その倍の費用がかかることになります。例えば、20,000円の供花を「一対」で注文すると、合計金額は40,000円となります。
「一基」と「一対」の違い
- 一基(いっき):スタンド花1つ。個人で贈る場合はこちらが一般的。
- 一対(いっつい):スタンド花2つ(1セット)。費用は一基の2倍。故人と極めて近しい関係の場合に用いられる。
伝統的に、祭壇の両脇に同じ花を対称に飾ることで、祭壇全体が荘厳で華やかになるため、「一対」で贈ることが正式な形とされてきました。しかし、斎場のスペースの問題や、葬儀全体の規模が縮小している現代では、個人から贈る場合は「一基」でも全く失礼にはあたりません。むしろ、個人からの供花は「一基」で贈るのが一般的になっています。
「一対」で供花を贈るのは、主に故人の子供一同や兄弟姉妹、あるいは法人や団体など、故人と非常に近しい関係の場合や、特に深い弔意を示したい場合に限られることが多いです。注文の際に「一つお願いします」と曖昧に伝えると、「一基」のことなのか「一対」のことなのかで混乱を招く可能性があります。「2万円のもので、いっきお願いします」というように、単位を明確に伝えることが、意図通りの手配につながる重要なポイントです。
友人一同で出す供花の相場

学生時代の仲間や会社の同僚など、友人同士が連名で「友人一同」として供花を贈ることは、一人ひとりの経済的負担を抑えつつ、故人への感謝と弔意をしっかりと形にできる非常に良い方法です。この場合の相場は、参加する人数や故人との関係性によって柔軟に考えられます。
一般的には、一人あたり3,000円から10,000円程度を出し合い、集まった総額の予算内で供花を選ぶケースが多いようです。例えば、5人の友人が集まり、一人5,000円ずつ出し合えば、合計25,000円となり、個人で贈る場合よりもボリュームのある立派な供花を手配することが可能になります。
名札の書き方と取りまとめ役の仕事
名札の表記は、シンプルに「友人一同」とするのが最も一般的です。もし、特定のグループ(例:「〇〇大学 平成〇年卒一同」「元〇〇株式会社 営業部有志」など)として贈りたい場合は、そのように記載することも可能です。
連名で供花を出す際には、誰かが代表して取りまとめ役を務める必要があります。この取りまとめ役は、想像以上に重要な役割を担います。
取りまとめ役の主なタスクリスト
- メンバーへの連絡:供花を贈る提案をし、参加者を募る。
- 金額の設定:一人あたりの金額を決め、全員の合意を得る。
- 集金:参加者からお金を集める。立て替える場合は後日清算する。誰から受け取ったか明確に記録しておく。
- 葬儀社への注文:代表して葬儀社に連絡し、予算、名札の表記、支払い方法などを伝達・確認する。
- 支払い:集めたお金で支払いを行う。
- メンバーへの報告:手配が完了した旨と、もし余剰金や不足金が出た場合はその清算について報告する。
友人同士で誰がその役を担うか、事前にしっかりと話し合っておくことが、後のトラブルを避けるために大切です。特に集金に関しては、後から「言った、言わない」の問題にならないよう、グループチャットなどで記録が残る形でやり取りをすると安心です。
葬式の花を孫一同で贈る値段

祖父母の葬儀に際して、孫たちが連名で「孫一同」として供花を贈ることも、深い愛情と敬意を示す素晴らしい方法であり、ご遺族(自分たちの親世代)にとっても大変喜ばしいことです。
この場合の費用は、孫の人数や年齢構成、それぞれの経済状況によって大きく異なりますが、総額で20,000円から50,000円程度の範囲で手配されることが多いと考えられます。
例えば、まだ学生や社会人になりたての若い孫が多い場合は、一人あたりの負担を考慮して総額20,000円から30,000円程度の一基を贈ることが現実的でしょう。
一方、孫全員が社会人として独立している場合は、より立派な30,000円から50,000円程度の供花や、故人への深い感謝を示すために一対(60,000円~100,000円)で贈ることも選択肢に入ってきます。
取りまとめと名札の表記
通常、孫一同で贈る場合は、孫の中で最年長者が取りまとめ役となるのが最もスムーズです。最年長者が中心となり、兄弟姉妹やいとこに連絡を取り、一口あたりの金額(例えば「一口5,000円でどうだろうか」など)を提案し、集金して代表して葬儀社に注文を行います。
名札の表記は「孫一同」とするのが一般的です。孫の人数が多い場合、全員の名前を列記すると非常に読みにくくなってしまうため、「孫一同」とまとめるのがスマートです。もし人数が3名程度と少ない場合は、年齢順に右から全員の名前を記載することもあります。その際、結婚して姓が変わった孫がいる場合でも、旧姓ではなく現在の姓(フルネーム)で記載するのが一般的ですが、地域の慣習などもあるため、親世代に確認するとより安心です。
どのような形であれ、孫たちが心を一つにして祖父母を想う気持ちが最も大切であり、その想いは必ずご遺族にも伝わります。
葬儀の供花代は誰が払うもの?

葬儀の供花代は、誰が支払うべきかという疑問を持つ方もいるかもしれませんが、答えは非常にシンプルです。その供花を**「贈りたい」と考えた個人や団体が支払います**。
供花は、故人への弔意やご遺族への慰めの気持ちを形にして「贈る」ものです。したがって、その費用は贈り主が負担するのが当然の原則となります。
- 個人名で贈る場合:その個人が全額を支払います。
- 「株式会社〇〇」として贈る場合:会社の経費として処理され、会社が支払います(一般的に勘定科目は福利厚生費や接待交際費として処理されます)。
- 「友人一同」として贈る場合:参加した友人たちがお金を出し合って支払います。
時折、喪主やご遺族が供花代を支払うのではないかと誤解されることがありますが、そのようなことは一切ありません。喪主やご遺族は、あくまで供花を「受け取る側」です。贈り主が支払いを済ませた供花を受け取り、感謝の気持ちと共に祭壇に飾って故人に供えるのが一連の流れです。
供花の手配を葬儀社に依頼した場合、支払いはその葬儀社に対して行います。支払い方法は、葬儀社によって異なりますが、当日斎場の受付で現金で支払う、後日請求書が送られてきて銀行振込で支払う、あるいはクレジットカード決済に対応している場合もあります。注文時に支払い方法についても確認しておくと安心です。
葬儀に参列できない場合のメール例文と供花まとめ
この記事では、やむを得ず葬儀に参列できない場合のメールの書き方から、弔意を示すための供花のマナー、手配方法、費用相場までを詳しく解説しました。大切なのは、故人を悼む気持ちと、ご遺族に余計な負担をかけないよう配慮する心です。最後に、本記事の重要なポイントをまとめます。
- 参列できないお詫びメールは件名だけで内容が分かるようにする
- メールでは時候の挨拶は不要で本題から入る
- 故人との関係や参列できない理由を簡潔に述べる
- ご遺族の心労を気遣う言葉を必ず添える
- 供花を贈る際はまずご遺族が辞退していないか確認するのが最優先
- 宗教・宗派によって適した花が異なるため注意が必要
- 供花は通夜の開始時刻までに届くように手配するのが望ましい
- 手配先は葬儀社に直接依頼するのが最も確実で安心
- 注文時は故人名、喪主名、日時、場所などの情報を正確に伝える
- トゲのある花や香りの強い花、派手な色の花は避けるのがマナー
- 家族葬の場合は特にご遺族の意向を尊重する
- 個人の供花相場は15,000円から30,000円が目安
- 供花は一基(いっき)という単位で数え、一対(いっつい)はその倍の価格
- 友人一同で出す場合は一人3,000円から10,000円程度で集める
- 供花代は贈り主が負担するものでご遺族が支払うことはない


